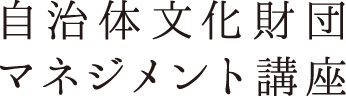About受講者の声 2017
自治体文化財団マネジメント講座に参加して

井上 鏡子
公益財団法人 いばらき文化振興財団
「財団としてどうしていけばよいのか、その取組を一緒に考えてくれる場所があるかもしれない」ということが手元に届いたパンフレットを見た最初の感想でした。文化財団は設立の背景等が異なっているため、すべての財団に共通した課題解決方法はありませんし、「こうしよう」と考えても、「これで正しいのだろうか」といった不安がついてまわります。1年間、4回にわたって考える場、教えていただける場をいただけたことは、本当に幸いでした。
今回の講座は『人材育成』を柱に据えました。その中で特に印象に残っているのは財団の目的はミッションの達成であるはずであるが、日常の中で「事業が目的化していないか」「職員が日常考えているか」というお話でした。すべての職員が、財団のミッションと現在置かれている立場を共有し、危機感を持って業務に取り組んでいけるようにするため、今回の講座で考えた2年間のスケジュールを、来年度以降着実に進めていきたいと思っております。


成島 洋子
公益財団法人 静岡県舞台芸術センター(SPAC)
SPACが設立して22年、活動は幅広く広がり、国内外での評価も高まっています。しかし一方で静岡県の予算状況は厳しく、SPACへの財政支援も減少する中、SPACを県が支える意義、その公益性について、そしてSPACのファンや支える人を増やすにはどうしたらいいかということを県の文化政策課と一緒に考えました。
しかし今回の講座を通じ私が何よりも実感したことは、設立から23年目を迎えるいま、設立の経緯を知る人も県にいなくなり、SPACの意義や公益性について改めて説明するための言葉・手段が必要だということです。特に予算を獲得するために県の財政課と折衝し、時には県民からの声を受け止める窓口となっている文化政策課の担当者が自らの言葉で納得して答えられる理解・体験を持つことの重要性を感じました。
講座での先生方のご指導や課題を通じ、また成果発表会でのコメントなど、多くの「第三者からの言葉」をいただいたことはとても重要な経験だったと言えます。「県の文化政策だから」、「いいことをやっているから」だけでは乗り越えられない壁を、乗り越えるための言葉を獲得する対策をSPACも講ずるべきだと実感したことが何よりの収穫でした。ご指導ありがとうございました。


丸藤 卓也
一般財団法人 こまき市民文化財団総務グループマネージャー
SUAC自治体文化財団マネジメント講座に参加し、こまき市民文化財団の抱える課題に取り組む機会を与えていただき誠にありがとうございました。こまき市民文化財団は、平成29年4月に小牧市により設立され、これまでの行政主体の文化施策からの転換として、専門人材の確保や中長期的な事業計画の立案、地域との連携など様々な課題を抱える中で大きな役割を期待されて設立されました。この立ち上がったばかりの文化財団にとって、進むべき大きな方向性であるミッション・ビジョンの策定は、組織のガバナンスとしても、市民に向けたメッセージとしても重要な意味を持つものであると感じています。今後は、ビジョン・ミッションを財団職員が共有し、長期的な視野に立った財団運営とともに事業や地域とのつながり中で実践をしていかなければならないと思います。
最後に、静岡文化芸術大学の高島先生をはじめ多くの先生、スタッフの方々の非常にきめ細かいご支援に対してあらためて御礼申し上げます。


野中 宏朋
一般財団法人 こまき市民文化財団事業グループ兼広報営業グループマネージャー
平成29年4月のこまき市民文化財団の設立とともに、事業グループ兼広報営業グループのマネージャーとして慣れない職務に専念し、自分自身を顧みる余裕もなく、慌ただしい日々を送っておりました。そんな中、貴学に通う財団職員がいるご縁もあり、本講座を知るところとなりました。毎日の膨大な仕事に追われている現状から、正直受講の申し込みを躊躇しておりましたが、興味深い内容であり、講座自体が財団の負担にならないように配慮がされていることなどから、思い切ってエントリーした次第です。
講座で検討する課題を設定し、協議を深める中、熱い松本先生、論理的な片山先生、冷静な高島先生のご意見、講評などで、財団の業務や存在意義から将来像までが学術的に検証されていく過程を通して、財団と自分を客観的に顧みることができました。また、講座を通じて財団のビジョン、ミッション、行動方針に専門的な助言をいただいて完成できたことは大きな喜びです。また、それらが意味するもの、その重要性について根本から考えることができた経験は、確固たる自信につながるものと確信しております。
本講座に携わっていただきました静岡文化芸術大学をはじめとするすべての方に厚く御礼申し上げます。

藤原 かほる
公益財団法人 岡山県文化連盟
3回の受講を通じて、施設のミッションは「共創」(=作家やユーザーと共に新しい芸術や文化的価値を創造する)であり、ネットワーク形成や職員のサポート、情報の収集・発信も、すべては「共創」のためという一定の結論に達し、ほっとしています。
最大の収穫は、客観的な視点が得られたことです。この企画は「誰のための、何のためのもの」なのか?それを文化連盟が行う意義は何か?という視点は今までなかったものでした。また、主催事業を4象限化したことで、「クリエイション」に至らない「文化の享受」に留まる事業が多いことも分かりました。これらは、今後、自主事業を企画・立案する上で職員が必ず持っておくべき視点だと思います。
同時に、“共創”の場としてのハコの機能強化や、職員の人員体制など、公益社団法人である岡山県文化連盟では解決が難しい問題も浮き彫りになりました。行政のパートナーとして様々な提案ができるよう、施設管理者としての存在感を高める必要性を感じました。


中村 清和
公益財団法人 北九州芸術文化振興財団
講座を通して、財団が抱えている課題が明らかになり、解決に向けて市と共に考える機会を得たことは、大変有意義であった。財団のあるべき姿を考えた結果、市内の文化全般を牽引実践する組織として機能すべきことを改めて認識した。しかし、課題の解決は容易ではない。財団は雇用や財政の不安定さを持ち、指定管理事業中心の体制となっている。また、外郭団体としての制約や、市との関係性を抜きにして施策を考えることはできない。講座では、講師の先生方の誘導により、財団と市は、お互いの事情を改めて理解し、何ができ、何をする必要があるのかを考える機会が持てた。
短期雇用の職員が大半を占める中、急激な財団の改革は難しい。長期的な視点を持ち、職員の無期雇用化の流れを契機として、今回の議論を生かし、市との協議も続けながら、機動力のある新しい財団組織へと、まずは一歩を踏み出したいと考えている。


稗田 猛典
公益財団法人 北九州芸術文化振興財団
九州地区においては、芸術系大学も、文化政策を学べる機会もとても少なく、静岡文化芸術大学の先生方に北九州市までお越しいただいてハイレベルの議論をするという今回の講座は、たいへん貴重で有意義な機会でした。29年2月のキックオフ講座を東京で受講し、多くの参加者を目の当たりにしましたが、本市を選択していただいたことに、あらためて厚くお礼申し上げます。わずか3回のゼミナールでしたが、市と芸術文化振興財団の職員が現状・課題や危機感を共有できたことは、大きな成果でした。本市で開催していただいた公開セミナーでも、いろいろと参考になるお話を聞くことができました。
成果発表会の場では、本市行政全般の硬さ、他都市の柔軟さも再認識しました。抜本的なすぐの改革は難しいものの、できるところから手を付けていく必要があると考えています。引き続き、ご指導、ご助言をいただければ幸いです。ありがとうございました。
2017年度「SUAC自治体文化財団マネジメントセミナー」公開セミナー
アンケート結果
アンケートの回収状況について
| 会場 | テーマ | 開催日 | 受講者数 |
|---|---|---|---|
| 茨城 | 地域と歩む文化・芸術団体の人材育成 | 12月19日 | 20 |
| 静岡 | ファンドレイジング | 12月22日 | 21 |
| 北九州 | 自治体の政策と地域を牽引する文化施設 | 1月9日 | 39 |
| 名古屋 | 地域を育てる民間非営利組織 ~ミッション・ビジョンの重要性~ | 1月10日 | 18 |
| 岡山 | 多層的ネットワークと拠点づくり | 1月27日 | 16 |