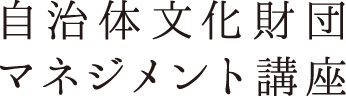Archive茨城会場 意見交換会
公開セミナー茨城会場「地域と歩む文化・芸術団体の人材育成」意見交換会
職員が主体的に行動する組織文化の形成
職員が主体的に行動する組織文化はどのように形成をされたのか?
米本:2004年に職員配置計画を策定し専門的なプロパー人材の雇用という方針を掲げたことで、従来の市主導型の在り方を変える方向へ転換したことがきっかけだと考えます。
安田:県職員の引き上げに伴い民間職員を登用したこと、指定管理者制度導入を受けて多様な分野の民間出身者を中心に知恵を出し合い財団のサービスを改善した、という2つが今の組織文化が形成されたターニングポイントだったと思います。
安田:県職員の引き上げに伴い民間職員を登用したこと、指定管理者制度導入を受けて多様な分野の民間出身者を中心に知恵を出し合い財団のサービスを改善した、という2つが今の組織文化が形成されたターニングポイントだったと思います。
自治体文化財団の運営における設置自治体の影響
自治体文化財団の人員管理を設置自治体がコントロールするという話があったが、その仕組みはどのようなものか?
米本:かすがい市民文化財団の場合は、財団と設置自治体がほぼ一体の関係にあり、財団職員の配置計画は財団と市が協議して決定しています。市の財団に対する理解があるため、職員数及び身分保障がしっかりされており大変助かっています。
安田:三重県文化振興事業団の場合は、職員の増員についてその人件費を自館で賄うという自助努力を県から求められます。その点において、かすがい市民文化財団とは大きく異なっているなと感じます。
安田:三重県文化振興事業団の場合は、職員の増員についてその人件費を自館で賄うという自助努力を県から求められます。その点において、かすがい市民文化財団とは大きく異なっているなと感じます。
ガバナンスにおける理事や評議委の存在
公益財団法人や一般財団法人のガバナンスという点において、理事や評議員から意見や議論が出ることもあるのでしょうか。
米本:かすがい市民文化財団はボトムアップを基本としています。中間管理職が集まるマネージャー会議の役割が非常に大きく、現場の問題はここで方針を決めることが多いです。とはいえ、ボトムアップの組織でもトップの意見は重要で、理事長から全職員に向けてお話をいただく機会を設けています。今は、中部大学の元学長が理事長を務められているのですが、非常に気軽に来ていただいて職員と自由にお話をされています。そういった意味でも、財団内の風通しは役員も含めて良いと思います。
安田:三重県文化振興事業団の場合、常勤の副理事長兼事務局長が実務のトップを担っていて、そのメッセージ性は非常に重要です。事業団の所属長が集まる会議には、非常勤の理事長にも出席いただき全体の状況を把握してもらいます。財団の制度が公益財団法人に変わったことで理事長への責任が非常に重くなっていますので、その理事長への説明責任として私たち職員は事業団の現状をお伝えするよう努めています。
安田:三重県文化振興事業団の場合、常勤の副理事長兼事務局長が実務のトップを担っていて、そのメッセージ性は非常に重要です。事業団の所属長が集まる会議には、非常勤の理事長にも出席いただき全体の状況を把握してもらいます。財団の制度が公益財団法人に変わったことで理事長への責任が非常に重くなっていますので、その理事長への説明責任として私たち職員は事業団の現状をお伝えするよう努めています。
職員育成と地域の関係
組織内に限らず地域社会が職員を育てるという側面もあるかと思うが、そういった事例について何かあるか?
戸舘:人材育成は多義性のある言葉だと思います。公共ホールの人材育成事業の中には、市民公募のワークショップを人材育成事業に位置付けているところも見られます。内部の職員向けの研修等を人材育成として位置付けているだけではなく、組織の外に向けた事業を人材育成として位置付けています。
安田:三重県文化振興事業団では、「ミエ・アートラボ」というプロジェクトチームが作る研修があります。この研修には県内外から多くの方が参加されるのですが、可能な限り自館の職員にも研修として一緒に受けさせています。そのため、同じ館の職員の中で研修の主催者側と参加者が混在するという構造になっています。
米本:かすがい市民文化財団でも、「ミエ・アートラボ」や愛知県芸術劇場主催の中堅職員のための劇場職員セミナーに参加していますが、主催館の職員が多く参加されているので、ネットワークをつくりやすい環境があります。講師として派遣された研修に、私よりも経験を積んだ方が参加されていたりもするので、人材育成というのはどちらかが一方的に与えるものではなく、互いに高め合う機会として捉えています。
安田:三重県文化振興事業団では、「ミエ・アートラボ」というプロジェクトチームが作る研修があります。この研修には県内外から多くの方が参加されるのですが、可能な限り自館の職員にも研修として一緒に受けさせています。そのため、同じ館の職員の中で研修の主催者側と参加者が混在するという構造になっています。
米本:かすがい市民文化財団でも、「ミエ・アートラボ」や愛知県芸術劇場主催の中堅職員のための劇場職員セミナーに参加していますが、主催館の職員が多く参加されているので、ネットワークをつくりやすい環境があります。講師として派遣された研修に、私よりも経験を積んだ方が参加されていたりもするので、人材育成というのはどちらかが一方的に与えるものではなく、互いに高め合う機会として捉えています。
地域の文化団体とのコミュニケーションの取り方
地域の文化団体とのコミュニケーションの取り方について、何かありますでしょうか?
米本:かすがい市民文化財団は2000年に設立されたため、地域の文化関係者の方が春日井の文化をより深く知っています。そのため、地域の文化関係者200人と共同で事業に取り組んでいます。一緒に仕事をしていると、細かな調整など大変なこともありますが、それをやることによって本当に地元に根付いた財団になれると思います。地域の若手音楽家、美術家の支援事業に取り組んでいるのですが、そこで巣立った方に新しく先生方になってもらうことで世代交代も進んでいき、地域文化が継承されていくのではないかと考えています。
採用・求める人材像について
米本:職員採用の際は、経験というよりも熱意や発想といった人間力を見るということを心がけています。エントリーシートの中に、「最近見た文化・芸術について印象に残ったものを1つあげて、具体的に感じたことを書いてください」という質問をすることがあるのですが、その回答を見ると人柄が分かります。大学生の回答の中にも「中学生の時に見た」といった記述がみられるのですが、発想が興味深ければ審査に通ることもあります。一方で、私たちの方から大学の就職説明会に参加することもあるのですが、実は学生の反応はあまり良くありません。文化・芸術の業界に入りたい学生が一番に目指すのは、東京の有名な劇場や有名なアーティストの制作をやっているところだったりします。そういう意味では私たちも選ばれる側にあり、地元の文化施設を就職先として希望する人がいなくならないよう、特に労働環境改善に向けた活動は積極的に行っています。
安田:三重県文化振興事業団は総合職採用をしています。そのため、アートマネジメントを学んできたからといって必ずしも文化会館に配属されるとは限らず、施設の維持管理に回ることもあります。その点は個別面接のときに必ず確認をしています。総合職採用には専門性が発揮できないという短所はあるのですが、一方で専門が特化しすぎると偏ってしまうこともあるので常識的な視点を持ってやっていくということが大切だと思っています。