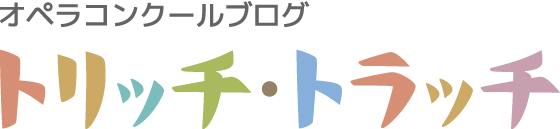【ふじやまのぼる先生のオペラ講座(17)】
前回は、上演する場所の言語で上演していたというお話をしました。
言葉が混ざる?
客演で来たけれども、その国・その歌劇場で上演している歌詞がわからない時はどうしていたのでしょう。そんな時は、歌える言語で歌ってもらったこともあったようです。先生が持っているCDで、1933年から1944年にかけてのウィーン国立歌劇場の録音があります。音質はあまり良いとは言えませんが、戦前戦中の上演を知る全24巻CD48枚の貴重な資料です。当時はウィーンの言語であるドイツ語での上演がほとんどでしたが、下記に示したように、1936年6月7日の「アイーダ」公演では、みなドイツ語で歌っている中で、スウェーデン人の客演歌手ユッシ・ビョルリンク(1911-1960)だけがスウェーデン語で混ざるという奇妙な現象が起きていました。
.jpg)
いろいろなオペラが収録されているこのCDの前提として、上段に「特段の提示がなければ、すべての演奏はドイツ語で歌われている(ピンクの部分)」と三か国語で書かれています。そして、「ユッシ・ビョルリンクはスウェーデン語で歌っている(黄緑色の部分)」とのただし書きがあります。1つ目はアリアなので、特に問題ないですが、2つ目からはアンサンブルになるので、ちょっと妙な感じがします。もっとも原語(イタリア語)に慣れている耳からすると、他の歌手のドイツ語による「アイーダ」も違和感がありますね。
統一しましょう
しかしこのブログでもよく登場する指揮者ヘルベルト・フォン・カラヤン(1908-1989)が、「オペラは創られた言語で上演すべし」との方針を打ち出し、1960年ごろ、ちょうどウィーン国立歌劇場の音楽監督だった時から徐々に原語で上演される方式に変わっていきます。
オペラはまず台本があって、それに作曲していきます。作曲家は言葉のイントネーションや聞き取りやすさを考えて作曲しますから、当然作曲された原語が良いわけです。訳詞は完ぺきに原語と同じというわけにはいきませんので、多少(多大)意訳もあります。そういったわけで「一流」と呼ばれる歌劇場では原語主義が広まっていきました。
その代わりと言ってはなんですが、ウィーン国立歌劇場で合唱団員として所属していた方にこんなお話を伺ったことがあります。公演の際「外国語ボーナス」というのがあったそうです。ウィーンはドイツ語を母国語としているので、それ以外のオペラが上演されるときにはちょっとだけボーナスがついたとのことです。
それでもやっぱり訳詞上演にこだわるという劇場もあり、ウィーンのフォルクスオーパーやミュンヘンのゲルトナープラッツ劇場、ベルリンのコーミッシェオーパーなどは、ほとんどのオペラをドイツ語で、ロンドンのイングリッシュ・ナショナル・オペラは英語で上演しています。フォルクスオーパーで観たドイツ語の「カルメン」、フランス語の流れるような言葉が、エキサイティングなゴツゴツに変わっていて、興味深かったです。