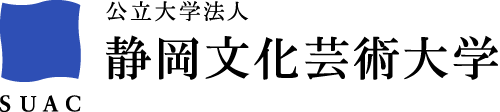在学生・卒業生の声Voices
大学院でのプロジェクトにより、
リアリティを感じて設計に取り組めた。
中村 紀章 さんNAKAMURA Noriaki
デザイン学部 空間造形学科 2004年卒業建築家 /京都芸術大学 専任講師
兵庫県神戸市出身。静岡文化芸術大学第1期生としてデザイン学部空間造形学科に入学。卒業後、筑波大学修士課程芸術研究科に進学し、都内の設計事務所を経て、2012年「中村×建築設計事務所」設立(共同主宰)。2020年4月より京都芸術大学専任講師。

ターニングポイントは「オープンデスク」
大学の進学先を迷っていたとき、幼いころに通っていた画塾に通い始めました。絵を描くことや建築、家具などに興味があり、文系でも建築を学べるSUACに出願。完成間近の大学を見に浜松を訪れたとき、当時再開発中の大学周辺を歩き、気持ちの良い風が吹く気候が気に入ってSUAC進学を決めました。当時在籍していた「空間造形」という学科では建築に限らず空間にまつわる様々な授業を受けましたが、建築分野に進むと決めたターニングポイントは、3年次に行った「オープンデスク」でした。設計事務所などに出向き実務を経験するもので、主に住宅を扱う大阪にある事務所で2週間活動しました。専門用語が飛び交う現場で面白さを感じ、4年次には寒竹研究室(建築・都市デザイン)に所属。卒業後の進路を考える中でより幅広い知識を学びたい、他大学での学びも経験してみたいと思い大学院への進学を決めましたが、卒業制作の講評は散々でした。建築には多様な考え方が存在するので落ち込む必要はないと先生になだめられたことを覚えています。
「寺島町リノベーションデザインワークショップ」(2016年)
浜松の築35年のアパートを学生のデザインによって改修するプロジェクト。大きな土間に面した建具の開閉によって間取りを変化させる。実際の賃貸物件として住まわれている。
浜松の築35年のアパートを学生のデザインによって改修するプロジェクト。大きな土間に面した建具の開閉によって間取りを変化させる。実際の賃貸物件として住まわれている。
プロジェクトでリサーチの面白さを学ぶ
進学した大学院は、一期生として入ったSUACではいなかった“先輩”の存在が大きな違いでした。所属した貝島研究室は設計の前段階となるリサーチを重視していて、プロジェクトの中でリサーチの面白さを学ぶことができました。学部時代の設計課題では架空の施主を想定しなければならず、ある意味で責任のない自由な発想をすることが出来ましたが、大学院のプロジェクトではその場所に関わるあらゆる事象を考慮し、学部時代とは違ったリアリティを感じて設計に取り組むことができました。研究室ではチームで設計することが多く、自分の発想をどのように伝え他人と共有していくのかという視点を改めて深く考えることにも繋がりました。
「寺島町リノベーションデザインワークショップ」の様子。天内准教授(本学デザイン学部)もワークショップ講師として参加。
より豊かな場所をつくりあげるのが建築
修了後は東京にある個人設計事務所に勤め、その後一級建築士資格を取得。その頃、寒竹先生からSUACのプロジェクトを手伝ってくれる人を探しているということで声がかかり、母校に戻ることになりました。後にSUACでは非常勤講師も務めることになり、後輩たちへの指導の機会もいただきました。現在では浜松で当時知り合った人たちやSUACの後輩たちと一緒にプロジェクトに取り組むこともあります。そもそも建築はいろんな分野の様々な関係者とともに場所を作り上げていきますが、そういったプロジェクトでは各々の人脈から多くの登場人物が関係することによってより豊かな場所をつくりあげることができると感じています。
神戸に建つ新築の戸建て住宅。L型の平面形状をしており、建物の裏側に周囲の建築に囲まれた中庭的空間を持つ。既成サッシを組み合わせた大きな開口部は縁側のように働く。
一緒に建築の在り方を模索する
現在は活動の拠点を神戸に置き、2012年に同じく建築家である兄と共同で設計事務所を立ち上げました。設計に取り組むうえで大切にしているのはクライアント(施主)と一緒に「まち」について考える、ということ。クライアントの注文通りに作るのでも、建築家の提案通りに作るのでもなく、住む人が社会と接点をもつ空間を持ち、「まち」をつくる一員となるような建築を目指しています。京都芸術大学の講師に着任してからの学生との向き合い方も同じです。建築には一つの答えがあるわけではありません。それを学生と一緒に考えて建築の在り方を模索する、そんな空間を大切にしていきたいと思っています。
神戸の商店街に面した小規模保育園の改修。商店の連なりに参加するように大きな庇を構え、内部は布のテープをルーバー状に並べることで、自然光を柔らかく室内に反射させている。
内容は取材時(2020年7月)のものです。