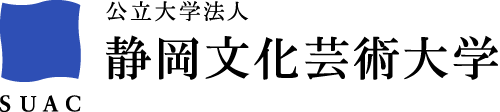イベントレポート
2024年11月06日
「第18回 社会調査インターカレッジ発表会」が開催され、文化政策学科 舩戸ゼミが発表しました
東海地方の各大学の協力のもと、社会学関係者や市民団体で構成される「東海社会学会」が共催し、毎年、「社会調査インターカレッジ発表会」を開催しています。
この発表会では、大学の授業やゼミで実施した聞き取り調査やアンケート調査委の結果を報告します。
18回目を迎える今年は、10月20日(日曜日)に、本学で開催され、本学をはじめ愛知大学・中京大学・名古屋市立大学・名古屋大学・浜松学院大学が参加しました。
今回の発表会には、「高校生の部会」も設け、県内からは掛川西高等学校、浜松西高等学校、袋井高等学校が参加し、「探究学習」の成果について報告しました。本学からは、文化政策学科 舩戸ゼミが参加し、現在、ゼミで取り組んでいる浜松の中山間地域についての調査結果を発表しました。

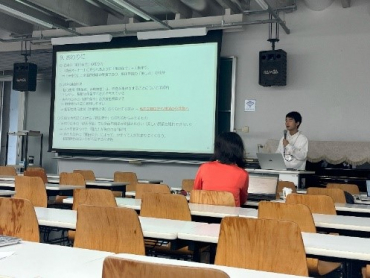
文化政策学科4年生の植田勝也さんが「棚田と地域住民とのかかわり-浜松市浜名区引佐町久留女木地区の事例から-」というタイトルで、地元住民への聞き取り調査から久留女木地区にある「棚田」の保全に関する地元住民の考え方の相違について報告しました。
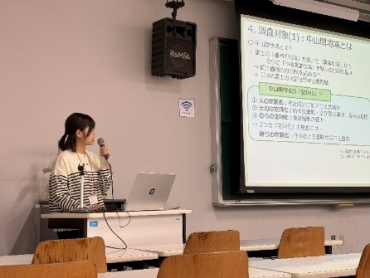
同学科同学年の冨田菜々美さんが「集落から転出した子どもと出身集落とのかかわり-浜松市天竜区佐久間町の事例から-」というタイトルで、浜松市天竜区佐久間町のある集落で実施した「他出子(転出した子ども)」へのアンケート調査から他出子と出身集落との関係性について報告しました。

同学科同学年の森田瑞希さんが「『消滅集落』における元住民と集落とのかかわり-浜松市中山間地域の事例から-」というタイトルで、浜松市中山間地域で常時居住していない「消滅集落」の元住民への聞き取り調査から今もその集落に通い続ける理由や意味について報告しました。
今回は、高校教員や高校生など、例年よりも多い100名以上の参加者があり、それぞれの発表に対して多くの質問が出され、活発な議論を行うことができました。
次回の「第19回 社会調査インターカレッジ発表会」も、来年秋頃開催される予定です。発行部署:企画室