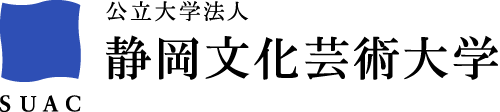教育・研究
2024年07月22日
「掛川茶フェアトレード」の取り組みについて特別講義が行われました
国際文化学科専門科目「フェアトレード論」 (担当:武田淳准教授)にて、 掛川市が取り組む「掛川茶フェアトレード」の取り組みについて、掛川市職員を招いた特別講義が行われました。
講師の萩田さんは掛川市産業経済部お茶振興課に所属。茶業の振興に特化した部署がある自治体は珍しいといいます。掛川市の特産として茶業の推進するため、さまざまな取り組みをおこなっています。掛川のお茶

お茶の種類は「緑茶」「烏龍茶」「紅茶」の3種類に分けられ、その違いは発酵の度合い。すべて同じ茶樹から作られています。さらに緑茶は製法や加工方法によって味わいや渋みに差が生まれ、「煎茶」「玉露・かぶせ茶」「深蒸し茶」「碾茶(抹茶)」に分類されます。掛川の特産は深蒸し茶で、日本一の深蒸し茶産地として全国茶品評会で産地賞を全国最多25回受賞するなど、高い技術力が全国で認められています。
茶畑で栽培された茶葉が加工され、消費者に届くまでには「生産者」と「茶商(お茶問屋)」が関わっています。茶畑で茶葉を栽培し、お茶工場で第一次加工された「荒茶」をつくるまでが生産者の仕事。その後、茶市場を経て、茶商による第二次加工によって「仕上げ茶」が製造されます。現在、掛川市内の茶生産者は約540戸、茶商は約40社。市内の多く人が茶業に携わり、支えています。
約150年前(江戸末期~明治)からはじまった掛川でのお茶栽培は、開国後の日本にとって有力な輸出品として重宝されました。日照時間が長い掛川のお茶は、渋みが強いのが特徴でしたが、昭和30年前後に茶業関係者が一丸となって、「深蒸し茶」の研究をおこない、掛川茶ならではの深蒸し茶が生まれました。昨今ではお茶の健康効能も注目され、海外でも人気があります。掛川の茶業の課題

一方で、一世帯当たりのリーフ緑茶(急須で淹れて飲む茶葉)購入量は、約40年で2分の1に減少し、平均購入額を上回るのは60代以上の世帯のみとなっています。ペットボトル緑茶ドリンクの登場を機に、消費者は急須を使わない手軽な緑茶ドリンクを選択する傾向が増加。若年層の緑茶離れの傾向もみられます。
主にリーフ緑茶に使用される「一番茶」と、主に緑茶ドリンクに使用される「二番茶」「秋冬番茶」の茶葉の価格は、リーフ緑茶購入量の減少により価格の高い一番茶の需要が減り、茶葉の価格が年々下落。荒茶の価格もピーク時の2分の1に減少しました。茶生産者の収入が減少していることが要因となり、10年間で約6割(約880戸)の生産者が経営を終了。経営茶園面積も10年間で約3割(約470ヘクタール)減少しています。生産者の後継者不足も顕著な課題です。掛川茶フェアトレードの取り組み
このような課題を抱える中、「掛川茶未来創造プロジェクト(掛川市茶振興計画)」を令和4年6月に策定。「生産」「消費」「流通」まで一貫した施策を推進しています。「流通」の施策として取り組んでいるのが、掛川市ではこれまで長い慣習の中で行われている荒茶の流通構造を見直し、生産者の持続可能な経営を目指した「掛川茶フェアトレード」です。
「フェアトレード」というと主に途上国との商品や原料の輸出入での公正な取り引きがイメージとして強いですが、もともとフェアトレードはさまざまな社会課題を解決するための方法として、柔軟に運用されてきました。今回の掛川市での課題でも、「フェアトレード」を切り口に、持続可能な荒茶取引(茶業版フェアトレード)環境の整備に向けた取り組みをはじめました。
これによって生産されたお茶を「茶業版フェアトレード品」として認証し、掛川茶振興協会が認証製品であることを消費者に周知してくことで、エシカル消費や選択購入を促進していきます。

発行部署:企画室