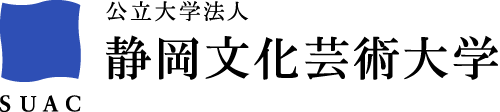教育・研究
2024年12月19日
「博物館実習」にて浜松市秋野不矩美術館学芸員の方をゲスト講師に刀剣(日本刀)取り扱い特別授業を開催(12月12日、13日実施)
本学 芸術文化学科では、学芸員養成課程を開設しています。
この学芸員養成課程の「博物館実習」では、博物館に係る実務に則しながら学芸員としての心得や技能を培うことを目的とし、博物館運営に関われる実践的な能力を養っています。

田中宏子さん
浜松市秋野不矩美術館学芸員
芳賀町総合情報館、刀剣博物館、東京都美術館の学芸員を経て2023年より現職。主な担当展に「福田たね 青木繁のロマン」(2008、芳賀町総合情報館)、「花鳥絢爛 刀装 石黒派の世界」(2016、刀剣博物館)、「上野アーティストプロジェクト2019 子どもへのまなざし」(2019、東京都美術館)がある。
浜松市秋野不矩美術館学芸員
芳賀町総合情報館、刀剣博物館、東京都美術館の学芸員を経て2023年より現職。主な担当展に「福田たね 青木繁のロマン」(2008、芳賀町総合情報館)、「花鳥絢爛 刀装 石黒派の世界」(2016、刀剣博物館)、「上野アーティストプロジェクト2019 子どもへのまなざし」(2019、東京都美術館)がある。
刀剣の歴史について学ぶ

刀剣は古来より三種の神器のひとつとして登場するなど神の依り代としての役割や、江戸時代の武士は二本差しを許され身分の象徴として用いるなど、さまざまな役割を果たしてきました。また、世界にも類をみない貴重な美術工芸品としても親しまれています。平安中期以降に制作技法が確立した日本刀は時代に応じて長さや反り、重さなど変化しており、鑑賞ポイントにもなっています。
刀剣(日本刀)の鑑賞方法について学ぶ
授業の後半では、実際の刀剣(日本刀)を扱った鑑賞方法を学びました。
準備として事故防止のために時計やネックレスなどのアクセサリー等はすべて外した後、刀身を汚さないよう手洗いを入念に行います。
日本刀には主に「姿」、「地鉄」、「刃文」の3つの鑑賞ポイントがあり、鑑賞方法が異なります。学生は緊張感ある空気の中、作法を学びながら鑑賞しました。実習では2口の刀が用意され、比較することでより具体的に刀の重さ、地鉄や刃文の違いなどを感じていました。
準備として事故防止のために時計やネックレスなどのアクセサリー等はすべて外した後、刀身を汚さないよう手洗いを入念に行います。
日本刀には主に「姿」、「地鉄」、「刃文」の3つの鑑賞ポイントがあり、鑑賞方法が異なります。学生は緊張感ある空気の中、作法を学びながら鑑賞しました。実習では2口の刀が用意され、比較することでより具体的に刀の重さ、地鉄や刃文の違いなどを感じていました。

姿の鑑賞の様子

地鉄の鑑賞の様子

刃文の鑑賞の様子
日本刀の手入れ方法について学ぶ

鑑賞後は刀身の手入れ方法や抜き方、納め方について学びました。
学生は道具である拭い紙や打粉(うちこ)などを使い、一連の手入れ方法について一人ずつ実践しました。刀剣を所蔵する美術館、博物館では定期的に学芸員がこの手入れ作業を行っていることもあり、ケガをしない様、慎重に講師指導のもと作業を行いました。
学生は道具である拭い紙や打粉(うちこ)などを使い、一連の手入れ方法について一人ずつ実践しました。刀剣を所蔵する美術館、博物館では定期的に学芸員がこの手入れ作業を行っていることもあり、ケガをしない様、慎重に講師指導のもと作業を行いました。
発行部署:企画室