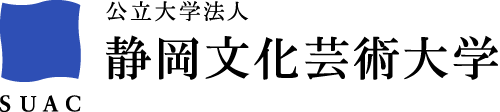教育・研究
2025年04月23日
国際文化学科・内尾太一研究室の防災研究が静岡新聞で紹介されました
国際文化学科・内尾太一研究室の南海トラフ地震に関する取り組みが、2025年4月9日付の静岡新聞(朝刊第1面の見出しおよび社会面)にて紹介されました。
記事では、浜松市に登録された津波避難施設における収容の適切性を評価するため、同研究室が作成した「津波避難収容指標」や、それに基づく実証実験の様子が詳しく報じられています。
その指標は、地域人口と避難スペースの関係を可視化するもので、今年3月上旬に市のホームページでもオープンデータ活用事例として公開されました。
記事では、浜松市に登録された津波避難施設における収容の適切性を評価するため、同研究室が作成した「津波避難収容指標」や、それに基づく実証実験の様子が詳しく報じられています。
その指標は、地域人口と避難スペースの関係を可視化するもので、今年3月上旬に市のホームページでもオープンデータ活用事例として公開されました。
これを基に3月下旬には、市内沿岸地域に設置された津波避難タワー(高さ7メートル、広さ150平方メートル)において、地元自治会の協力のもと、研究室の教員・ゼミ生たちが実証実験を実施しました。

事前準備として、レジャーシートを1平方メートル(行政が想定する1人あたりの避難面積)、0.75平方メートル、0.5平方メートルに切り分け、避難後の混雑の度合いを体験的に再現しました。


そして実証実験当日、津波避難タワーの上階で、同じサイズのシートを4枚組み合わせることで、隣り合う人とのパーソナルスペースを把握し、各サイズの座った状態・横になった状態、避難リュックの中身を広げた状態など、避難時の状況を多角的に検証しました。



参加したゼミ生(国際文化学科3年生 ※当時)の声
実験を通じて、狭いスペースで他人と密接して隣り合って寝る状況は、プライバシーの欠如や心理的ストレスの大きな要因となると感じた。今後は、空間の確保だけでなく、避難者同士の距離感への配慮や、心理的なケアを含めた工夫が必要であると感じた。また、避難場所の意義について、単に人数を収容するだけでなく、その場での必要最低限の質をどう保つかを考えることが重要だと学んだ。(安竹ひなた)
実際に1人あたりの避難スペースの範囲を可視化してみると、考えていたよりもかなり過ごしにくいことを痛感した。特に、学生同士と学生と大人、また男女差によっても同じ範囲でも感じ方が異なっていた。また、避難グッズについても自分と周囲を比べてしまい、自分に無いものを羨ましく思ったりと、心も身体も心地よく過ごせる避難スペース作りには多くの課題がまだまだあると感じた。(井出美優)
1平方メートルの空間は緊急避難時には十分と感じたが、災害時の異常事態では正常なメンタルではいられないかもしれない。体格差や男女差などによって必要な空間は柔軟に考えていかなければいけないと感じた。また実際の避難を想定して防災リュックを用意してみると、ポンチョ型のカッパが様々な場面で活躍するのではないかと新しい発見もあった。今後もゼミのメンバーで災害について考えていきたい。(渥美開登)
津波緊急避難場所でのスペースの確保がいかに重要かを、身をもって実感できた。特に、1人あたりのスペースが0.5平方メートルに満たなくなった場合、足を伸ばして横になることもできず、隣の人とかなり密着して過ごさなければならない。このような環境では、せっかく避難できたとしても、心身ともに落ち着くことは難しい。緊急避難場所での滞在環境について、私たちはもっと関心を持つべきであると感じた。(諸岡幸恵)
緊急避難場所での滞在が一日以上に及ぶ可能性もあることを考えると、精神的にも身体的にも厳しいものだと痛感した。性別だけでなく、高齢者や外国人住民への配慮など柔軟な対応を考えていく必要があると感じた。最後に各自準備した非常持ち出し袋の紹介を行い、他のゼミ生からも沢山のアイデアを得た。災害に対する関心や危機感を深めるよい機会になった。(白石彩音)
私の住む地域は海から少し離れているため、津波避難タワーに避難する想定をしたのは初めてだった。タワーの上で最も強く感じたのは、この高さで本当に津波から逃れられるのか、ということであった。仮に無事だったとしても、その場所で長時間過ごさねばならない場合、季節や天候などの環境要因によっては、避難してからが本当に過酷な状況になることを学んだ。(米田朱里)
この実践的研究は、緊急避難場所における「圧迫感」や「プライバシーの欠如」といった課題を、学生たちが身体感覚として体験し、地域住民との対話を通じて現場の実情を理解する貴重な機会となりました。
実験を通じて、1人あたりのスペースが同じでも、体格差や性別、心理状態によって感じ方が大きく異なることが明らかになりました。また、避難生活の質を左右するのは単なる収容人数ではなく、精神的な安定や人間関係の距離感、物資の充実など多様な要素であることが学生たちの気づきから浮かび上がりました。
こうした体験により、避難自体の重要さに加え、「避難後」に想定される状況への理解が深まりました。避難スペースの設計、防災グッズの工夫、避難行動要支援者への配慮など、実践を通じた課題提起が今もゼミ内で議論されています。
実験を通じて、1人あたりのスペースが同じでも、体格差や性別、心理状態によって感じ方が大きく異なることが明らかになりました。また、避難生活の質を左右するのは単なる収容人数ではなく、精神的な安定や人間関係の距離感、物資の充実など多様な要素であることが学生たちの気づきから浮かび上がりました。
こうした体験により、避難自体の重要さに加え、「避難後」に想定される状況への理解が深まりました。避難スペースの設計、防災グッズの工夫、避難行動要支援者への配慮など、実践を通じた課題提起が今もゼミ内で議論されています。
発行部署:企画室