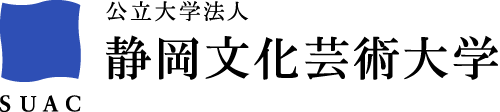教育・研究
2025年07月08日
「演劇文化論」にてゲストを迎えた特別講義を実施しました
文化政策学部学部科目「演劇文化論」(担当:芸術文化学科・永井聡子教授)では、講堂を教室として、演劇と劇場の歴史や本質的な視点を多角的に講義しています。
舞台芸術の現場で活躍する一流アーティストによるゲスト回では、6月19日に人形遣い・豊松清十郎さんにお越しいただきました。
舞台芸術の現場で活躍する一流アーティストによるゲスト回では、6月19日に人形遣い・豊松清十郎さんにお越しいただきました。

「文楽の歴史」「文楽の三業」「人形遣いと女方」「国立劇場、国立文楽劇場などの舞台」をキーワードとした対談に加え、実演、学生参加の体験、学生からの質疑応答などあわせて90分の講義でした。

永井教授より
豊松清十郎さんは、私が劇場(知立市文化会館)のプロデューサー時代からのご縁で、開館5周年記念「文楽人形創作オペレッタ 池鯉鮒宿祭乃縁」(助成:文化庁芸術拠点形成事業)を企画・制作したときに出演していただき、オリジナル新作舞台を仕上げた経緯があります。2008年に大学に着任してからは、毎年のように「演劇文化論」のゲストにお越しいただいています。文楽協会からご持参くださる人形を人間のように遣う清十郎さんの技術から繰り出される表現力に驚く学生も多く、見る側の視界から人間が消えることを目の当たりにし、学生は伝統芸能の歴史といまを感じたようです。
学生のコメント
「三人遣いの人形を、豊松清十郎さん1人だけでも、頭と右手を操作することで、あんなにも繊細に喜怒哀楽を表現できるのが興味深かったです。」「いかに人間のように人形を扱い、人間を越えるか?の言葉が印象に残りました。」「文化継承という点から考えると、人気がないからやらないのでは、次の世代につなげていくことができないため、歴史ある文楽を残していくために、需要に関わらず公演することの重要性を学びました」「動かない人形に命を吹き込むことの素晴らしさを目の前で体験することができました」
なお、本講義の各ゲスト回では、制作アシスタントに永井ゼミ生(三年生、四年生、大学院生)が参加しています。
発行部署:企画室