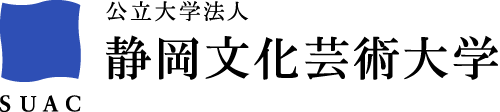教育・研究
2025年07月25日
「演劇文化論」にてゲストを迎えた特別講義を実施しました

文化政策学部学部科目「演劇文化論」(担当:芸術文化学科・永井聡子教授)では、講堂を教室として、演劇と劇場の歴史や本質的な視点を多角的に講義しています。
舞台芸術の現場で活躍する一流アーティストによるゲスト回では、7月10日に日本舞踊家・花柳源九郎さんにお越しいただきました。
舞台芸術の現場で活躍する一流アーティストによるゲスト回では、7月10日に日本舞踊家・花柳源九郎さんにお越しいただきました。

左:講義の様子、右:「源氏物語」より「葵の鏡」
新作舞踊作品「源氏物語」より「葵の鏡」(初演)の披露をはじめ、講義として「日本舞踊の魅力-着物・和楽器・言葉」「役柄と役割」などと、学生参加のワークショップをあわせて90分の講義でした。

ワークショップの様子
永井教授より
新作舞踊作品として、「源氏物語」から「葵の鏡」を企画と脚本を担当。約10分の作品に収めたものを学生の前で初演しました。事前に、私から作品、作曲について、また演出の花柳源九郎さんから言葉や舞踊表現の意図を解説し、見どころを伝えた上で鑑賞してもらいました。鈴や笛の間合い、扇子や打ち掛けだけで表現する見立て、登場しない葵の上を表現する女形の振付など、シンプルな中にも登場人物の嫉妬や葛藤などの心情を感じとることや表現として理解するという、劇的な作品を鑑賞する際の想像力を育むまたとない機会となったと思います。
企画・脚本・舞台監督・プロデューサー 永井聡子
作曲・笛・ナレーション 藤舎推峰
演出・振付・舞踊・謡(声) 花柳源九郎
学生のコメント
「葵の鏡では、言葉と着物や扇子を他のものに見立てて表現する様子が印象的で、日本舞踊は想像力をかき立てられるものであると感じました」「衣裳やセットがほとんど無いのに、嫉妬に駆られる六条御息所が見えて驚きました」「推峰さんの鈴の音の間合い、笛の音色、らしさの追求のための仕草の工夫が見えて、伝統芸能の奥深さを感じました」
なお、本講義の各ゲスト回では、制作アシスタントに永井ゼミ生(三年生、四年生、大学院生)が参加しています。
発行部署:企画室