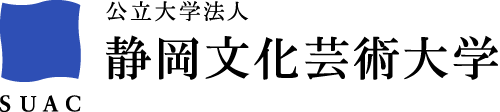教育・研究
2025年07月04日
デザイン学部植田道則教授の ―地域工務店・大工職人の「感覚的領分」と 変わりゆく生活者の美意識の存続継承活動― が内閣府の「第3回総合知活用事例」に 取り上げられました
デザイン学部植田道則教授の ―地域工務店・大工職人の「感覚的領分」と変わりゆく生活者の美意識の存続継承活動― が内閣府の「第3回総合知活用事例」に取り上げられました。
この活動は、同教授の科研費研究課題(課題番号23K04196)に基づくもので、総合知の活用方法の進化を目指す ものです。
「総合知」 とは、「多様な「知」が集い、新たな価値を創出する「知の活力」を生むこと」であり、
これらによって「知の活力」を生むことこそが「総合知」であり、「総合知」を推し進めることが、 科学技術・イノベーションの力を高めるものです。
(内閣府「総合知」ポータルサイトhttps://www8.cao.go.jp/cstp/sogochi/index.htmlより抜粋)
植田教授の研究課題では、生活の基盤である住まいに対し、在来木造を通じ大工職人が携えてきた経験と勘による技術の領域(暗黙知)と大工職人自らが醸成してきた美意識が統合された領域を「感覚的領分」と定義し、現代の生活者が抱く美意識との共通点・相違点を明らかにすることで、変化する価値観の中で、在来木造の質と生産性の向上、日本の美意識の継承を探求しようとするものです。今回、この研究内容が科学技術・イノベーションを高める内閣府の「総合知」の活用事例とされました。
この活動は、同教授の科研費研究課題(課題番号23K04196)に基づくもので、総合知の活用方法の進化を目指す ものです。
「総合知」 とは、「多様な「知」が集い、新たな価値を創出する「知の活力」を生むこと」であり、
- 多様な「知」が集うとは、属する組織の「矩(のり)」を超え、専門領域の枠にとらわれない多様な「知」が集うこと。
- 新たな価値を創出するとは、安全・安心の確保とWell-beingの最大化に向けた未来像を描くだけでなく、科学技術・イノベーション成果の社会実装に向けた具体的な手段も見出し、社会の変革をもたらすこと。
これらによって「知の活力」を生むことこそが「総合知」であり、「総合知」を推し進めることが、 科学技術・イノベーションの力を高めるものです。
(内閣府「総合知」ポータルサイトhttps://www8.cao.go.jp/cstp/sogochi/index.htmlより抜粋)
植田教授の研究課題では、生活の基盤である住まいに対し、在来木造を通じ大工職人が携えてきた経験と勘による技術の領域(暗黙知)と大工職人自らが醸成してきた美意識が統合された領域を「感覚的領分」と定義し、現代の生活者が抱く美意識との共通点・相違点を明らかにすることで、変化する価値観の中で、在来木造の質と生産性の向上、日本の美意識の継承を探求しようとするものです。今回、この研究内容が科学技術・イノベーションを高める内閣府の「総合知」の活用事例とされました。
植田教授コメント
「大切なのは人材育成と社会貢献で、その切っ掛けや依り代、柱として研究があると思っています。今後も、本学を通じた研究活動が、生活の質の向上に貢献できるよう、微力ながら努めます。」
発行部署:企画室