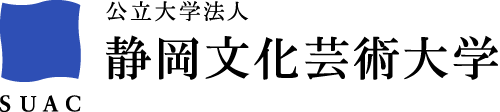- TOP
- 学部・大学院
- 教員紹介
- デザイン学部 教員紹介
- 花澤 信太郎
教員紹介

花澤 信太郎HANAZAWA Shintaro
教授
- デザイン学部 デザイン学科(建築・環境領域)
- 大学院 デザイン研究科
都市デザイン、建築デザイン、空間デザイン、風景とランドスケープ
| 出身地 | 千葉市 |
|---|---|
| 学歴 | 東京大学大学院工学系研究科 博士課程修了(2005年) |
| 学位 | 博士(工学)(東京大学、2005年) |
| 経歴 |
|
| 資格 | 一級建築士 |
| 担当授業分野 | 空間計画、建築設計演習Ⅰ、都市デザイン特論 |
| 研究分野 | 都市の空間構成 |
| 研究テーマ | 日本近世の都市空間 |
| 研究業績 | 著書
|
| 受賞歴 |
|
| 所属学会・団体 | 日本建築学会、日本都市計画学会 |
| 社会的活動 |
|
メッセージ
専門分野は都市と建築のデザインで、近世日本の都市景観とランドスケープの関係を研究テーマとしています。
「振り返れば未来」とは、本学の初代学長であった木村尚三郎先生の言葉ですが、しばしば歴史を知る事によって未来への手がかりを得られる事があります。ジョージ・オーウェルが未来世界として描いた1984年に、ウイリアム・ギブスンは『ニューロマンサー』を発表して、今日のサイバースペースでの戦争を予言しました。その小説の第一章の舞台となっているのは、私の育った街である千葉市の港の近くです。ギブスンはなぜ訪れた事もない千葉市を舞台に選んだのか? それは没個性的かつ無機質な未来都市として設定すべき街に、千葉市がふさわしいと考えたからだと思います。小説の中に想像で描かれた未来の千葉市の風景が、あの頃実際に体験したシーンとリンクして思い出される、奇妙なデジャビュの様な感覚を覚える時、ギブスンの深い洞察力を感じずにはいられません。しかし千葉港の夜空は、ギブスンが描いた「空きチャンネルに合わせたTVの色」ではなく、川崎製鉄の溶鉱炉で照らし出され「赤く染まって」いました。現実は、時として想像を超えるのです。
私がこれまでに見た偉大な建築もまた、想像を超える空間を持っていました。ギザの大ピラミッド、アテネのアクロポリス、ローマのパンテオン、イスタンブールのアヤ・ソフィア、パリのノートル・ダム、フィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ。これらの建築は、時間を超えて私たちに語りかけ、その空間はどんなにAIが発達しても、現実の中でしか得られない体験と感動を与えてくれます。
それでは、これらの偉大な建築はどの様に着想されたのでしょうか。これらに共通しているのは、突然それが現れたのではなく、習作ともいえる前段階の建築や、既にある建築の観察や分析を経て構想・建設されたという点です。建築は精神の着想と物理的な建設行為により形成されますが、今度は出来上がった建築空間が人間の精神に働きかけるのです。都市や建築は常に私たちの周りにあって心と体に語りかけている、この様な観点に立つと、たとえ小さな空間であっても、それは私たちに大きな可能性を提供してくれると言えるのではないでしょうか。また変化の激しい時代にあっても、都市や建築のデザインはその使用年数の長さから、過去から現在を経て未来へ向かう永い視点に立脚する事が大切であると考えられます。