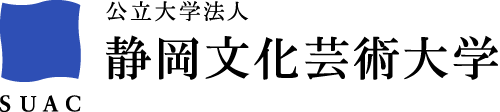ゼミ紹介・卒業研究演習
ゼミ紹介

作品を言葉で表して
美術と歴史を紐解く
ゼミでは、美術作品をまず言葉で丁寧に記述して、それから先行研究を調べて同時代の資料にもふれ、モチーフの意味や主題について考察します。さらに注文の経緯や当初の設置場所などから、作品を取り巻く環境について分析します。このような過程を経て、なぜその作品が生み出され、どのように受容されたのかなど、作品と文字資料から読み取れる情報を客観的・歴史的に分析し、美術作品の意味や社会との関わりについて考えます。
藪田 淳子 講師(西洋美術史)

一枚の絵から広がる、
時代と思想の物語を読み解く。
美術館で解説書を読んだことがきっかけで、美術史に興味を持ちました。絵画の歴史的背景や画家の思想を知ると、作品がより深く理解できることに魅力を感じ、藪田ゼミを選びました。現在は、ゲインズバラの《ブルー・ボーイ》に焦点を当て、ファンシー・ピクチャーというジャンルの研究を進めています。ゼミでは、文献の探し方や作品 分析の方法を学び、自分の疑問を深掘りする力が身につきました。美術をさまざまな視点で学べるのがSUACの魅力です。
森平 風花(芸術文化学科3年、愛知県立半田東高等学校出身)
注:学生の学年表記は取材時(2024年度)のものです。卒業研究演習一覧
現地調査を通じて音楽と社会に向き合う
担当教員 :梅田英春 教授
世界中の音楽は社会と深く関わっています。ゼミ生は民族音楽学の基礎を学んだ後、国内外で音楽に関するフィールドワークを1人で行い、その成果をもとに音楽と社会の繋がりについて考えます。過去の音楽文化から「現代社会」を考える
担当教員 :奥中康人 教授
地方創生の掛け声の下で ―「B級グルメ」や「ゆるキャラ」のように― 音楽を利用するのはもうウンザリ。身近な音楽に目を配り、文化や芸術の枠組み自体を再考してゆくことを目的としています。残された美術作品に向き合う
担当教員 :片桐弥生 教授
日本美術史の基本的な研究方法を、実際に作品をじっくり見て、研究論文などを読むことで身につけます。残された美術作品が制作当時、何を意図して作られ享受されていたのか明らかにすることを目指します。西洋の音楽文化・音楽と社会の関係を探る
担当教員 :上山典子 教授
西洋を中心とする音楽文化や、音楽と社会、音楽と政治、音楽と戦争などをテーマに、基本文献から最新の論文までを読み、議論を重ねることで、知識と視野を広げていきます。文化・芸術活動を担う人々や団体を見る
担当教員 :高島知佐子 教授
文化・芸術活動を経営の視点から見ます。フィールドワーク(現地調査)を通して、活動内容や活動の背景を紐解きます。また、社会に関する文献を多く読み、理論と現場から思考力・分析力を養います。現代芸術・視覚文化への理論的アプローチ
担当教員 :谷川真美 教授
多様な形態をみせる現代の芸術や、日常生活をとりまく様々な視覚文化について、芸術の歴史と思想を手掛かりとしながらその本質について考え、私たちの生きる現代とはどういうものか考えます。演劇・劇場の学問は現場から生まれる
担当教員 :永井聡子 教授
演出理念、空間、運営のメカニズムを分析する力を養います。帝国劇場、築地小劇場、東京宝塚劇場が海外の演劇史と作品を革命的に変えたように、観客が仕上げる演劇の本質を理論と実践から探究します。舞台芸術創造環境と地域社会に関する研究
担当教員 :佐藤良子 准教授
地域社会に息づく音楽や舞台芸術の姿を見据えながら、それを取り巻く環境・制度についてフィールドワークを交えた質的調査によって実態を把握し、政策との関わりを考察します。博物館・美術館の機能と役割を考える
担当教員 :田中裕二 准教授
コレクションを収集して収蔵庫で適切に保管、調査研究した成果を展示するといった基本的な機能がいま揺らいでいます。収集から公開・活用方法の検証と博物館の社会的な役割について考えます。劇作品を内(内容)と外(背景)から考える
担当教員 :稲山 玲 講師
戦後日本の劇作家たちが生み出した作品の中から具体的な作品を取り上げ、そのテキスト、演出を分析します。加えて、上演当時の社会背景、制作環境を調査することで総合的に作品を考察します。西洋演劇の創造と国際演劇交流の研究
担当教員 :田ノ口誠悟 講師
台詞劇、オペラ、バレエ、ミュージカルなど西洋出自の舞台芸術の分析手法を学びます。また、西洋演劇の日本における受容、海外戯曲翻訳・翻案といった越境的な演劇文化の交流についても考察します。芸術文化を通して皆が憩える広場を創る
担当教員 :南田明美 講師
芸術文化を通して社会的弱者が声をあげやすい場を創るには、どのような要素が必要なのか。そもそも芸術文化の力とは何なのか。質的調査を通して、それらの問いを追究していきます。西洋の美術作品から美術と社会の関係を考える
担当教員 :藪田淳子 講師
西洋の美術作品が生み出された社会背景や政治経済、各地域の文化交流に留意しながら、西洋美術史の基礎を学びます。先行研究を整理して作品分析を行い、美術と社会の関わりについて考えます。卒業論文発表会
芸術文化学科では、卒業研究の成果を発表するために、毎年2月に「卒業論文発表会」を開催しています。テーマは古今東西の芸術に関するものから、芸術文化政策・アートマネジメントにかかわるものまで多種多様。卒論発表会には、卒業生も、新年度入学予定者も集まるので、「ゲイブン」での4年間にわたる研究の集大成に接しながら、交流する機会にもなっています。