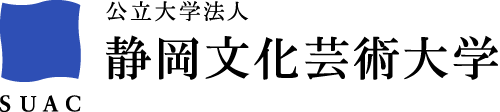- TOP
- 学部・大学院
- 教員紹介
- 文化政策学部 教員紹介
- 奥中 康人
教員紹介
奥中 康人OKUNAKA Yasuto
教授
- 文化政策学部 芸術文化学科
- 大学院 文化政策研究科
近現代の日本音楽史、鼓笛隊とラッパ、和洋折衷音楽、ムード歌謡、浜松ご当地ソング
| 学歴 | 大阪大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学 |
|---|---|
| 学位 | 博士(文学)(大阪大学、2002年) |
| 経歴 |
|
| 担当授業分野 | 音楽史Ⅱ、芸術特論C、文化資源論(大学院)など |
| 研究分野 | 音楽学 |
| 研究テーマ | 日本における西洋音楽の文化変容 |
| 研究業績 | 著書(単著)
|
| 受賞歴 | 第30回サントリー学芸賞(芸術・文学部門)(著書『国家と音楽 伊澤修二がめざした日本近代』に対して) |
| 所属学会・団体 | 日本音楽学会、東洋音楽学会 |
メッセージ
音楽研究者にとって、浜松は特別な街かもしれません。なぜなら、世界的に有名な楽器メーカーや、世界的なレベルのコレクションを誇る楽器博物館が存在するからです。
しかし、わたしにとっては、大学院時代のゼミの「浜松旅行」で――それが私の最初の浜松訪問だったのですが――、鍵盤ハーモニカを作る小さな工場(まさに町工場)の見学をしたことのほうが、強く印象に残っています。よく考えてみると、どんな大手の楽器メーカーにも下請け工場があるわけです。そこではごく少人数で小さな部品が製作され、そうした小さな部品をたくさん組み合わせることによって、はじめて楽器は完成するという、ごく当たり前のことに気づかされました。
ちょうどその頃、幕末から明治時代にかけての西洋音楽の流入に関心があったので、研究テーマとして、幕末維新期の鼓笛隊やラッパについて調べようとしていたところ、同じ大学院に所属していた(浜松出身の)後輩から「浜松では今でもラッパを使ってますよ」と聞いて仰天。さっそく導かれるまま浜松を再訪したのは2003年のゴールデンウィークだったと記憶しています。
「西洋楽器とはベートーヴェンやモーツァルトを演奏するための道具である」という私の固定観念を軽々と壊してくれたのは、中田島の凧揚げ会場や駅前の大通りで繰り広げられる爆音ラッパのパフォーマンスで、これまで音楽研究者が「西洋音楽の受容」として注目してきた音楽文化とは全く別の、いわば「西洋楽器の土着化現象」とでもいうべき実態にカルチャーショックをうけたことは、私の研究にとって大きな転機でした。
それ以来、毎年GWには、ビデオカメラを片手にラッパの音を追いかけながら調査をしているのですが、そうした足元にある身近な音楽文化――あまりにも卑近すぎて「文化」とは思えない人もいるかもしれませんが――を再考し、再評価することが、実は地域社会の芸術文化を考えるうえで、とても大切なことではないだろうかと思ったりしています。