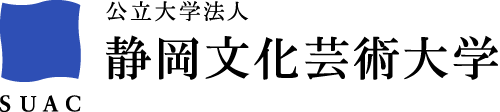- TOP
- 学部・大学院
- 教員紹介
- デザイン学部 教員紹介
- 倉澤 洋輝
教員紹介
倉澤 洋輝KURASAWA Hiroki
講師
- デザイン学部 デザイン学科
ホームページURL:https://kdo.co.jp/
キーワード:
グラフィックデザイン、エディトリアルデザイン、タイポグラフィ、工芸
| 学歴 | 京都精華大学大学院芸術研究科 博士前期課程修了(2006年) |
|---|---|
| 学位 | 修士(芸術)(京都精華大学、2006年) |
| 経歴 | 京都精華大学 非常勤講師(2010年から2020年) 京都造形芸術大学(現 京都芸術大学) 非常勤講師(2014年から2020年) 京都精華大学 デザイン学部 ビジュアルデザイン学科 特任准教授(2020年から2025年) 静岡文化芸術大学 デザイン学部 講師(2025年から) |
| 担当授業分野 | 基礎演習C(グラフィック) 領域専門演習 総合演習 |
| 研究分野 | グラフィックデザイン、エディトリアルデザイン |
| 研究テーマ | 美術館などで開催される展覧会の広報物、図録、出版物のデザイン制作 |
| 研究業績 | 研究業績(作品・プロジェクト)
|
メッセージ
現在では多くの人々が自分のキャリアを複数の軸で形成しています。クリエイターに求められる知見も、単一の専門領域を深く理解した上で、さらに領域横断的な幅広い知識や経験も求められています。
私自身は、大学入学から大学院までは陶芸(伝統工芸から陶磁器によるオブジェ制作などの立体表現)を学んでいました。大学院卒業時からデザイン業界に進み、以後は美術館などで開催される美術工芸領域の展覧会をグラフィックデザインによって、その魅力を広く伝えることを実践しています。工芸とデザインから得た知見を再解釈し、人々の興味を引く視覚表現を作り出せるように試行錯誤を続けると同時に、グラフィックデザインの知見を活かした工芸作品の制作・研究にも取り組んでいます。
私自身は、大学入学から大学院までは陶芸(伝統工芸から陶磁器によるオブジェ制作などの立体表現)を学んでいました。大学院卒業時からデザイン業界に進み、以後は美術館などで開催される美術工芸領域の展覧会をグラフィックデザインによって、その魅力を広く伝えることを実践しています。工芸とデザインから得た知見を再解釈し、人々の興味を引く視覚表現を作り出せるように試行錯誤を続けると同時に、グラフィックデザインの知見を活かした工芸作品の制作・研究にも取り組んでいます。