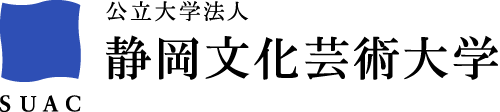- TOP
- 学部・大学院
- 教員紹介
- デザイン学部 教員紹介
- 佐藤 亜矢子
教員紹介

佐藤 亜矢子SATO Ayako
講師
- デザイン学部 デザイン学科
ホームページURL : https://asiajaco.com
キーワード:
現代音楽、電子音響音楽、アクースマティック音楽、サウンドデザイン、サウンドスケープ
| 学歴 | 東京藝術大学大学院音楽研究科 音楽専攻音楽文化学研究領域 博士後期課程 修了(2019年) |
|---|---|
| 学位 | 博士(学術)(東京藝術大学、2019年) |
| 経歴 | 東京藝術大学大学院音楽研究科 専門研究員(2019から2021年) 玉川大学芸術学部アート・デザイン学科 非常勤講師(2019から2025年) 東京電機大学工学部第二部 非常勤講師(2019から2021年) 大阪芸術大学通信教育部音楽学科 非常勤講師(2019から2025年) 尚美ミュージックカレッジ専門学校 非常勤講師(2022から2024年) 静岡文化芸術大学デザイン学部 講師(2025年から) |
| 担当授業分野 | サウンドデザイン、サウンドデザイン演習、領域専門演習 |
| 研究分野 | 現代音楽、電子音響音楽、サウンドデザイン |
| 研究テーマ |
|
| 研究業績 | 著書
【音楽作品発表(海外)】
【音楽作品発表(国内)】
|
| 受賞歴 | Seoul Independent Animation Festival、音・音楽特別賞(韓国、2022年) International UPISketch Composition Competition、カテゴリーC 第2位(フランス、2022年) International Destellos Competition、一般審査第3位、Foundation Destellos(アルゼンチン、2022年) Korea Independent Animation Film Festival、音・音楽特別賞、審査員特別賞(韓国、2019年) 東京藝術大学大学院アカンサス音楽賞(2014年) International Destellos Competition、アクースマティック音楽部門The honorary mention、Foundation Destellos (アルゼンチン、2013年) Prix Presque rien第3位、Association Presque Rien(フランス、2013年) International Taiwan Electroacoustic Music Composition Award、The honorary mention、WOCMAT(台湾、2013年) Contemporary Computer Music Concert、佳作、音と音楽・創作工房116 (日本、2012年) |
| 所属学会・団体 | 日本音楽学会(2020年から) 国際音楽学会(2017から2020年) 国際コンピュータ音楽協会 International Computer Music Association (ICMA)(2013年から) 先端芸術音楽創作学会(2012年から) 日本電子音楽協会(2011年から) |
| 社会的活動 | 日本電子音楽協会 理事(2024年から) Electroacoustic Music Studies Asia Network (EMSAN)編集委員(2024年から) TPMC(Tout Pour la Musique Contemporaine)作曲コンペティションpetites formes 審査員(2022、2024年) 先端芸術音楽創作学会 運営委員(2015年から) |
メッセージ
「サウンドデザイン」とは何でしょうか。一般的には、映画やアニメーションといった映像作品、テレビ・ラジオ番組、ゲーム、パフォーマンスなどに効果音を中心としたサウンドをつける技術や実践のことを指す場合が多いようです。しかし、私はこの用語をもっと広い意味で捉えています。
- 芸術作品の一部分としての音・音楽について考え、創造すること:美術領域の作品や展示において、音・音楽の存在が重要である場合は多々あります。サウンド・インスタレーションはもちろんのこと、絵画や工芸や写真や建築と音・音楽が共存することで成立する作品や展覧会やプロジェクトもあります。そこでどのように音・音楽が介入するのかを検討し、議論し、場を創造することも、サウンドデザインのひとつであると思います。
- 身のまわりにある/ない音・音楽について考え、創造すること:これはサウンドスケープ・デザイン、あるいはサウンドスケープ・コンポジションに繋がります。我々が暮らす世の中は、あまりにも多くの音・音楽で溢れています。人為的に創り出されたものもあれば、そうでないものもあります。過去には聞こえていたけれど、現在は我々の耳に届かなくなってしまった音・音楽もあります。そうしたさまざまな音・音楽を通して環境・社会について考え、快適な時間・空間を音・音楽によって設計することも、重要なサウンドデザインではないでしょうか。
私は作曲家、サウンドアーティストとして活動しています。リズム・メロディ・ハーモニーが音楽の三要素といわれますが、世の中にはそれを飛び越えた表現が多々あり、楽器で演奏するための楽譜を書く仕事ばかりが「作曲」ではありません。むしろ、私は上述した「サウンドデザイン」的なアプローチでの作曲やサウンドに関わる芸術作品・場の制作を主に行っています。環境音、現実音、物音、会話、雑音… どのような音も作品の素材になり得ます。我々を取り巻く環境に耳を傾け、さまざまな場所で出会った音を拾い集め(録音し)、それらを素材とした音楽作品やサウンド・インスタレーション制作、映像作品のサウンド制作、展覧会でのサウンド・ディレクションなどをしています。場所・空間・環境に関心をもっており、例えばそれはサウンドスケープ、空間音響といったキーワードに結びつきます。
学術的な側面からいいますと、現代音楽・電子音響音楽が専門分野です。とりわけ、リュック・フェラーリというフランスの作曲家が主たる研究題材です。フェラーリはピアノやオーケストラといった器楽のための楽曲のみならず、電子音響音楽、サウンド・インスタレーション、ラジオドラマ(ヘールシュピール)、映画など、幅広い領域の創作を手がけました。いつもその創造の根底には、ユーモアと、常識にとらわれない自由さと、新しい試みへの好奇心がありました。私は、そのような機知に富んだ彼の精神に感銘を受け、研究・創作活動をしています。固定観念にとらわれず、表現の可能性に一緒に挑戦していきましょう。