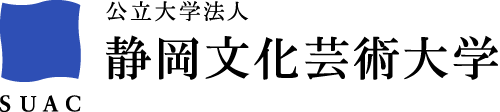- TOP
- 学部・大学院
- 教員紹介
- 文化政策学部 教員紹介
- 藤井 康幸
教員紹介

藤井 康幸FUJII Yasuyuki
教授
- 文化政策学部 文化政策学科
- 大学院 文化政策研究科
キーワード:
地域活性化、地域の個性、人口減少社会、持続可能都市、セクター協働
| 出身地 | 兵庫県西脇市 |
|---|---|
| 学歴 | 東京大学工学部都市工学科卒業(1986年) University of California, Los Angeles (UCLA), M.A., Urban Planning(1991年) 東京大学大学院工学系研究科都市工学専攻博士課程単位取得満期退学(2015年) |
| 学位 | 博士(工学)(東京大学、2017年) |
| 経歴 | 清水建設株式会社 地域開発部、神戸支店 ほか(1986年から2001年) 株式会社富士総合研究所/みずほ情報総研株式会社(現 みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)、都市・地域研究室、社会政策コンサルティング部 ほか(2001年から2018年) 静岡文化芸術大学文化政策学部教授(2018年から) 東京大学先端科学技術研究センター 都市環境システム分野 協力研究員(1993年から1995年、兼任) 筑波大学 システム情報工学研究科社会システム工学専攻 非常勤講師(2005年から2008年、兼任) |
| 資格 | 技術士(建設部門 都市及び地方計画) AICP(American Institute of Certified Planners、米国認定都市プランナー) 土地区画整理士 宅地建物取引主任者 |
| 担当授業分野 | 都市経営論、地域計画論、創造都市論、公共政策特講、ほか |
| 研究分野 | 都市・地域計画、まちづくり、創造都市 |
| 研究テーマ | 個性的で魅力ある都市、持続可能な都市、都市・地域にかかる計画と政策の領域 |
| 研究業績 | 著書・訳書
地域拠点都市、国際拠点都市、公共事業・サービスにおける公共と民間のパートナーシップ、米国のコミュニティ開発・アフォーダブル住宅供給、スローライフ、社会変化と都市政策、中心市街地活性化、都市再生、構造改革特区と対日投資促進、地方都市の再生戦略、集落コミュニティ、高齢社会、MICE、マンション建替、マンションコミュニティ、テレワーク、インバウンド観光、医療観光、コミュニティビジネス、防災政策 |
| 所属学会・団体 | 日本都市計画学会、日本都市学会、日本テレワーク学会、American Planning Association/American Institute of Certified Planners |
| 社会的活動 | 浜松市行政区画等審議会委員、東三河地域研究センタースマートリージョン研究会委員、シュリンキングシティ研究会メンバー(関連リンク)、ふじのくに地域・大学コンソーシアムゼミ事業(藤枝東海道宿、島田東海道宿、磐田敷地邑 関連リンク) |
メッセージ
都市・地域計画とまちづくりには、似ている面と異なる面があります。皆にとってより暮らしやすい都市・地域を目指すという点では共通する一方、都市・地域計画は、基本的には行政用語であり、もっぱら平仮名で表記されるようになったまちづくりは、都市・地域の物的な事項に加えて社会の様々な事項を扱う市民主体の取組を指します。
都市・地域計画、まちづくりの分野は間口が広く、かつ、対象や重点分野は時代の要請に応じて変化することが特徴的です。例えば、現在では、地球環境は都市・地域計画、まちづくりにおいて避けて通ることのできない課題となり、社会包摂も勘案すべき重要な事項と言えます。また、都市・地域計画、まちづくりにおいては、関連するセクター間の協働が肝要です。ここでいうセクターとは、行政、企業、市民団体、住民、大学や学校などです。どのセクターが発案、主導しようが、他の様々なセクターとのやりとりは必然となります。
都市・地域計画、まちづくりにおいては、スケール感と時間軸を意識して取り組むことが必要になります。例えば、地区や近隣コミュニティの問題と、広域的な緑地保全の問題では、スケールが異なり、アプローチは異なってきます。比較的、短期間に物事を決めて実施すべき事項もあれば、合意形成と実施に時間を要するような事項もあることでしょう。
創造都市は、文化・芸術、生活の質、革新的な産業とそのための人材など様々な切り口から、また、理論と実践の両面で注目の高まっているトピックであり、本学4学科の交差点的なポジションと解釈しています。
未来社会はますます複雑となることでしょう。そこでは、グローカルなものの考え方、対話、提案、他者理解といったスキルが重要となります。都市・地域、まちづくりの分野の学習や経験は、こうした考え方やスキルを養うに適したものに思います。湧き出る好奇心と豊かな発想をもって、授業や演習に参加していただくことを期待します。