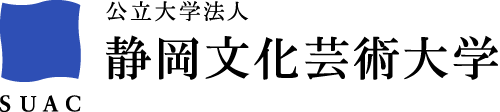- TOP
- 学部・大学院
- 教員紹介
- 文化政策学部 教員紹介
- 水谷 悟
教員紹介

水谷 悟MIZUTANI Satoru
教授
- 文化政策学部 国際文化学科
E-mailアドレス s-mizu@suac.ac.jp
キーワード:日本近現代史、「大正デモクラシー」、民主主義と大衆社会、近代日本の新聞・雑誌メディア、地方青年の言論空間
| 出身地 | 東京都世田谷区 |
|---|---|
| 学歴 | 筑波大学大学院博士課程歴史・人類学研究科(史学(日本史)専攻)単位取得退学(2003年) |
| 学位 | 博士(文学)(筑波大学、2014年) |
| 経歴 |
|
| 担当授業分野 | 歴史学、日本史学、文化交流論 |
| 研究分野 | 日本近現代史 |
| 研究テーマ | 集団の思想史(政治・思想・文化・生活・メディア・教育・地域社会) |
| 研究業績 | 著書
|
| 所属学会・団体 | 歴史人類学会、日本思想史学会、日本歴史学会、社会文化史学会、地方史研究協議会、メディア史研究会、日本史研究会、秋田近代史研究会、日本社会科教育学会、静岡県近代史研究会 |
メッセージ
これまで私は、近代日本における思想集団の結成と雑誌メディアによる思想運動の展開、それを支持した読者の実態を、政治・思想・文化・メディア・地域等の観点から解明してきた。主な例を挙げると、海老名弾正【牧師】率いる本郷教会に通う帝大生を中心とした新人会と雑誌『新人』(1900年創刊)、日露戦後に村井弦斎【作家】を編集顧問に迎えた婦人世界社と雑誌『婦人世界』(1906年創刊)、地方青年を結集し普選運動を展開した茅原華山【ジャーナリスト】ら益進会と雑誌『第三帝国』(1913年創刊)、第一次大戦後に反戦・平和を謳った小牧近江【思想家】ら種蒔き社と雑誌『種蒔く人』(1921年創刊)などである。
思想・言論の内容を重層的かつ多角的に捉えることは、日本の文化・社会の本質をつかむ上で重要であり、それらを発信している牧師・作家・ジャーナリスト・思想家らの存在は当時の政治・法律・経済・教育・生活・メディア・地域社会などの動向とも深く関わっている。今後も、「思想集団」「雑誌メディア」「読者」という三者の関係に注目しながら、個人と社会、中央と地方、日本と世界などをつなぐ思想的連関を一つ一つ解き明かし、「集団の思想史」研究を築いていきたいと考えている。
加えて、思想史研究で疎かにされがちである基礎的な史料調査を実施している。現在、静岡県下(浜松・掛川・藤枝・川根本町など)においてフィールドワークに取り組み、地域史料論ならびに地方ジャーナリズム論の分析を進めている。
また、教育の面では、担当授業により歴史学・日本史学の面白さを伝えるとともに、特にゼミでは「研究発表」「史料調査」「卒業論文」への指導を通してゼミ生たちが自らの意見を表現し議論することの大切さを知り、物事を歴史的に捉え、建設的な批判と創造的な提案ができる人物に成長していくためのサポートを心がけている。共に頑張りましょう!