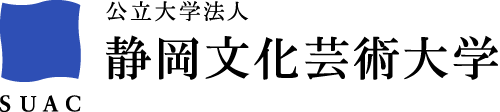- TOP
- 学部・大学院
- 教員紹介
- 文化政策学部 教員紹介
- 森 俊太
教員紹介

森 俊太MORI Shunta
特任教授 副学長 国際交流センター長
E-mailアドレス f8#7mori@suac.ac.jpキーワード:
ワークライフバランス、生きがい、留学、社会構築、週複数回授業
| 出身地 | 東京都大田区 |
|---|---|
| 学歴 | コロラド・カレッジ(社会学専攻)卒業(1982 年) カリフォルニア大学サンタクルズ校大学院社会学研究科博士課程前期修了(1984年) カリフォルニア大学サンタクルズ校大学院社会学研究科博士課程後期修了(1986年) |
| 学位 | 学士/B.A.(リベラル・アーツ)(コロラド・カレッジ、1982年) 修士/M.A.(社会学)(カリフォルニア大学、1984年) 博士/Ph.D. (社会学)(カリフォルニア大学、1994年) |
| 経歴 | カリフォルニア大学サンタクルズ校助手、助教、講師(1986年から1988年) インパクト・ジャパン株式会社 アウトドア研修人材開発講師(1989年から1990年) 静岡理工科大学 国際文化センター研究員・企画室長補佐(1991年から1996年) いわき明星大学人文学部社会学科助教授(1996年から2000年) コロラド・カレッジ社会学科/アジア研究学科客員教授(2001年から2012年、2018年から2019年) 静岡文化芸術大学助教授(2000年から2003年)、教授(2004年から2023年)、副学長(2020年から) 静岡文化芸術大学特任教授(2023年から)、国際交流センター長(2024年から) |
| 資格 | 専門社会調査士 |
| 研究分野 | 社会変動、社会構築論、比較社会、高等教育 |
| 研究テーマ | 静岡県内労働者の実態・意識・将来展望、ワークライフバランス、生きがい、大学カリキュラム |
| 研究業績 | 著書
|
| 受賞歴 |
|
| 所属学会・団体 | IDE大学協会 |
| 主な社会的活動 |
|
メッセージ
2020年4月に副学長に就任してから、設置者である静岡県によって求められる中期計画の策定と実施、県の評価委員会による実績評価への対応、外部評価機関である大学教育質保証・評価センターによる認証評価の準備、その評価結果を踏まえた教育研究に関する改善策の策定と実施等、大学の教学を中心とした役割を担ってきました。具体的には、教学IR委員会(組織情報を活用した改善活動組織)の設置と運用による教学マネジメント体制の開始、シラバスや授業アンケートの改善等による学修者本位の教育とその質保証のしくみの確立に、教務部長や学部長をはじめ関係者と取り組んできました。その結果、2025年度から全学的に、新カリキュラムとともに学修者本位の教学制度の運用を開始することができました。
国際交流を統括する立場では、海外の大学との留学生の交換、海外語学研修への学生派遣に尽力してきました。教職員と学生の努力の結果、近年は継続して多額の公的な留学支援資金を獲得し、多くの学生が支援を受け海外で学んでいます。
今後も、県西部に位置する公立大学として、地域社会と産業との連携拡大と深化、リカレント教育プログラムの充実、教員の研究力の更なる向上、教育研究活動に関する情報公開と学内のダイバーシティを推進します。また、教職員の協働体制を強化しながら、IRの対象を大学組織全体に広げ、教育研究と地域貢献の推進を目的とした、透明かつ公正な大学運営の確立に貢献します。
研究者としては、主に日本社会の変化について、生きがい観や、格差化、社会的包摂等の視点からの研究に取り組んできました。特に、現在にいたるまで20年以上、県内の研究所と共同で、静岡県内で働く人々の仕事と生活に関する多様な調査研究プロジェクトに参加しています。2025年からは「静岡県内労働者の実態と意識、将来展望」というプロジェクトに、労働、経営、行政各界の協力を得つつ代表として取り組んでいます。さらに大学のカリキュラム、特に学期や授業形態についての国際比較研究にも継続して取り組みます。
社会活動としては、国際人権NGO等で人権擁護活動をしていました。また海外での農業ボランティア活動にも従事しました。実務経験では、野外活動を研修方法として取り入れた人材開発研修会社(英国・日本)にて、国内外の企業や県内自治体を含む団体の海外派遣要員や多国籍・多文化の社員・職員を対象とした、チームワークやリーダーシップ、問題解決能力育成の指導をしました。
以上のように研究や社会活動、実務経験で、複数の国や地域に長期滞在しており、比較社会・比較文化の視点を得る体験を多く持ちました。このような経験を、大学運営、教育や研究、社会活動に活かしていきます。