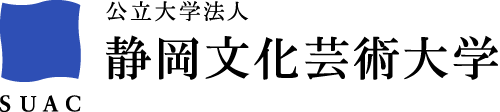- TOP
- 学部・大学院
- 教員紹介
- 文化政策学部 教員紹介
- 永井 聡子
教員紹介

永井 聡子NAGAI Satoko
教授
- 文化政策学部 芸術文化学科
- 大学院 文化政策研究科
キーワード:
舞台芸術論、劇場史、演劇史、演出、観客、劇場計画、劇場運営
| 出身地 | 岡山県 |
|---|---|
| 学歴 | 名古屋大学大学院工学研究科建築学専攻博士後期課程修了(2001年) |
| 学位 | 博士(工学)(名古屋大学、2001年) |
| 経歴 |
|
| 担当授業分野 | 演劇文化論、劇場芸術論、劇場プロデュース論、舞台芸術論など |
| 研究分野 | 演劇史、劇場史、演劇・ミュージカル・ダンスの舞台プロデュース |
| 研究テーマ | 演劇・劇場史研究、劇場・舞台作品プロデュース |
| 研究業績 | 著書
|
| 所属学会・団体 | 日本建築学会、日本演劇学会、日本文化経済学会、日本建築学会 文化施設小委員会WG委員(東京)、劇場演出技術協会(JATET)・建築部会委員(東京) |
| 社会的活動 |
|
メッセージ
劇場研究とプロデュース
「劇場」を「人」「作品」「空間」「観客」と定義して単著『新・舞台芸術史―劇場芸術の境界線を読み解く』(現代図書、2024年)を出版しました。演劇、舞台芸術、劇場の謎を解き明かす一冊です。実践と学問の境界から生み出される「劇場」の持つメカニズムを探究し続けたいと思っています。
大学院博士課程での研究後、劇場にプロデューサーとして10年勤務し、「地域の劇場」はどうあるべきかを考えながら、「演劇」や「ダンス」などの舞台作品の製作を行い、教員である現在でも続けています。
劇場における専門家の立場にいながら100人のボランティア市民の皆さんとの協働事業も進めてきました。市民の方々とともに、地域の「芸術・文化」を「財産」とするために、一丸となって事業に取り組んできました。「劇場」は「生きもの」です。劇場という「空間」を拠点にして、舞台の専門の領域で働く人々と地域の市民とのエネルギーがぶつかりあってまた新しい「地域の文化力」が生まれるということを実感してきました。
大学では、学生に演劇、舞台芸術、劇場の歴史や理論とともに、「現場」の持つ力を感じることや「現場力」を自らつけることができるよう「企画を実践する」という舞台製作の現場を体験する授業、そして演出家、舞台美術家など舞台芸術の専門家の存在を知る機会を設定して教育に努めています。
舞台作品の製作や研究、教育を通して、地域の文化が「創造」され「発信」されていく環境を創っていきたいと思います。